ボクと犬と [One's Boyhood story]
ボクと犬と
喧嘩ばかりしている小学時代には、自分がやったことではないのに、文句がきて、息子がやったかわからぬ悪戯に、いかにもやりそうだと母親は取りあえず謝っていた。
父が提案した。
喧嘩ばかりしないで、勉強もして、がんばるんなら犬を飼ってやる。
ボクは即座に誓い、約束を守った。
ボクは飼いたくて仕方がなかった犬を手に入れた。
スコッチテリアと日本犬の雑種で整った顔立ちの美人だ った。
どこへ行くにも一緒だったけれど、やはり彼女の序列では父が1番、自分が2番、ボクが3番で、母が4番目だったようだ。
彼女はボクと同じように岸壁から飛び込み、川を泳いで渡り、父と母の目を盗んで二階のボクの部屋に入り込んで寝た。
そのうち雑巾で足を拭いたら、家に上げてくれるということを覚え、僕らは感心して見ていたが、彼女には天候の良し悪しとかいうこととは関係なく、雨の日にも外で遊び長い毛先を泥だらけにしつつ、玄関先に雑巾を咥えてきて足だけ拭いて堂々とリビングで寝ていたりした。
夏休みになると朝からボクを「川へ行こうと誘った。」
ボクが物置に置いてある水中眼鏡と金突(銛)を手に取ると、全速力でボクの自転車まで走り、ペダルに前脚をかけて待っていた。
彼女を乗せるための補助椅子をつくって父がボクの自転車の前に付けた。
彼女は前脚をハンドルにかけ、補助椅子から立ち上がって、自転車のスピードに合わせて風を切って気持ちよさそうに目を細めていた。
その日小型だったけれど台風が過ぎて3日目のまだ、水量が収まっていないS川へ、ボクは彼女を自転車の前に乗せ、いつものように魚を捕りに行った。
目当ては水が出て、流れが変わった深みに彷徨い出ている大きなナマズであった。
また水流が早いとき、鮎は川上に泳ごうとしても水の抵抗で俊敏さを奪われている。
そこをボク達はチョン掛けと呼ばれる返しのない十字の針を付けた竿の先で引っかけて捕ったりした。
当然子供でも入漁券(鑑札)は持っていた。
でも、その日狙ったのは大型のナマズで、それはウナギと同じように捌いて蒲焼きにするととてもおいしかった。
母は祖母の代から使っている鰻の蒲焼き用のタレを持っており、それを付けて焼くと殆ど鰻の味であった。
堰堤を越えて流れる川の水はいつもより冷たく早い。彼女は淵に渦巻いている緩い流れの中に飛び込んでその淵に添って一周するたびに堤防側に上がり、全身をぶるぶるッと振って水を切り、ボクの様子をしばらく眺めてはまた淵に飛び込んでいる。
ボクは堰堤の傍の流れが速い淵に埋まった杭を掴みながら堤防の下に深く掘れ込んだ場所を一つ一つのぞいていった。
50センチくらいのナマズを一匹仕留め、口から鰓に縄を通し、逃げないように縛って堤防の裾にある四角いコンクリートの囲いのようなブロックの中に入れておいた。
ボクはそれよりはるかに大きいナマズの尻尾を見付けた。
それは上から倒木が覆い被さったコンクリートブロックの下にゆらゆらと見えていた。
ボクは倒木に両足をかけ、その上からゴムを引き、尻尾の長さから胴体の位置を測って、銛を打ち込んだ。
バッと川底の泥が跳ね上がり、雲のようにボクの水中眼鏡の視界を奪った。
でも、ボクは両手で銛の柄を掴み、体重をかけて突き通すくらいに強くつき込んだ。
確かな手応えはあったが、驚いたことにそのナマズは全く力が衰えず、銛の柄をへし折らんばかりに暴れた。
その時、ずるり…と足下の倒木が動き、ボクはバランスを崩して片足を水の中で泳がせながら必死で上を向き息を継いだ。
『どうしよう』と思ったが、名案が浮かばない。
片手で銛を押さえ込み、もう一方の手で倒木の枝を掴み、バランスを取りながら何とか流れの中にとどまっていた。
でも、その姿勢は、流れの速い川でいつまでもとれる姿勢ではなかった。
ボクにはもうわかっていた。ボクが突いたのは大きなナマズではなく、川の水が多くなり、浅い住処を追われ、塒を探している途中のオオウナギだということを。
「仕留めたい、」「逃がしたくない」という思いと、溺れることへの恐怖感の間で、小学5年のボクは迷いに迷っていた。
水面に顔が出たとき、ボクは堤防の上を笑いながら歩いてゆく銛を持った2人連れの青年を見つけた。
「たすけて」
と言ったと思う。
でも、その声が聞こえたのはボクの様子を見ていたボクの犬だけだった。
視界から遠ざかってゆく二人を見たとき、ボクはこの銛から手を放さなければならないことを感じた。
悔しかった。
その時なんだか大きな声がしてすぐ川上でザブン…と誰かが飛び込む音がした。遠くで犬が吠える声がする。
もうひとつの声は頭の上からだった。
「ボク。どうした?溺れてるのか?大丈夫かよ?」
その声のする方に、ボクは溺れているのではなく、オオウナギを銛で突いたのだが、尻尾あたりに命中したのでこのままでは逃がしてしまうことを水をしたたか飲みながらとぎれとぎれに伝えた。
「ユウちゃんカナツキ!」
たしかユウちゃんと言ったその声に応ずるようにボクのすぐ傍に水中から逞しく日焼けした青年の体が浮き上がった。
「どこだ?」その青年はボクの指す指の方向を辿り、もう一度潜って確認すると、すぐ浮き上がり、上からのぞき込むもう一人の青年に向かって言った。
「でかい。凄いよ。カナツキ、お前のもいるよ。」
「わかった今取ってくる。」駆け出していった青年はすぐに堤防の上から自分の銛を手にして駆け下りてきた。
「ボク。抑えてろよ。なるべく頭を狙いたいけど、でかすぎて頭がどこかわからない。胴を打って引きずり出すぞ」
ユウちゃんと呼ばれる青年は大きく息を吸い込んで潜り、せまいコンクリートブロックの下まで潜り込むと、自分の銛を打ち込んだ。
「ボク。これをしっかり持ってろ。大丈夫だな。」
ボクはうなずいて自分の銛と青年の銛を2本抱え込んだ。
その青年はもう一人から、もう一本銛を渡されると、そのまま小さなしぶきを上げて、川の中に潜った。
僕の手には、まだ、凄い力で銛の柄をよじろうとするオオウナギの力が伝わっていた。
コンクリートブロックの隙間からもう一度川底の泥が大きく舞上がったとき、僕の手にびりびりと伝わっていた獲物の力が唐突に抜けた。
青年がボクを見つけてから10分ほどしか経っていないと言うことだったが、ボクとっては凄く長い時間が流れていた。
川から上げたそのオオウナギは最後の銛で頭部を貫かれ、息絶えた1メートル35センチほどの体をブロックの上に横たえていた。
普通の鰻のように単色ではなく、茶色と黒の斑で、幅の広さはウツボのようだった。
ボクが突いた銛の一撃は尻尾の先から20センチ位のところで、これではこの大きな獲物の力は丸1日かかっても衰えなかったろうと思う。
子供の狙える獲物ではなかった。
ボクは助けて貰った礼を言ったが、この獲物を自分のものだとは言えなかった。
「ボク。その犬は君の犬か?」
「うん。」
「頭のいい犬だな。そいついきなり俺のカナツキのゴムを咥えて、ここへ引きずって来たんだぜ。」
青年は彼女がボクの声を聞いて、自分たちを呼びに来たことを面白そうに話した。
横たわった鰻を相手に、前脚でちょっかいを出しながら激しく尻尾を振り続け、フンフンと匂いをかぎ回っている彼女はすっかり獲物に気を取られていて、ボクのことなど忘れたかのように、旺盛な好奇心をオオウナギに集中させていた。
二人の青年は分け前を取らない変わりに何枚も彼女と鰻の写真を撮って帰っていった。
その晩、父が捌いたオオウナギは母の起こした七輪の炭火の中で香ばしい匂いを漂わせていた。大きすぎてナイフでなければ切れないような分厚い身をボクは口いっぱいに頬張っていた。
大味で脂っこすぎると言われるオオウナギだが、鰻を食べ慣れているボクの家では脂の抜き方からよくわかってた。ただ、父の大好きな骨せんべいは骨が太すぎてさすがにできなかった。
彼女は、珍しく、頭だけではなく、尻尾の方の身を皿に盛られ、皿の縁を前脚で抱え込む姿勢で一心にパクついていた。
もちろん彼女の活躍は父にも話してあり、彼女は当然の報酬にありついたのだった。
「半分はお前が捕ったようなもんだな。」
父がボクの犬に向かって呟くと彼女は皿から顔を上げ、タレで茶色くなった鼻面を舐め、顎をそらして父を見た。
その夜は父や母が寝静まるのを待って勝手口からボクは犬を抱え、自分の部屋のベッドの下にバスタオルを敷いて一緒に寝た。
目を閉じるとまだ流れの早いS川の水面とそこから突き出た倒木の下にナマズや鰻が泳いでいた。
ボクは突然最初に捕ったナマズをすっかり忘れてきたことを思い出した。
こらえきれない笑いがこみ上げて、両手でボクは彼女の鼻面も耳も一緒くたにくしゃくしゃに撫で回した。
彼女は迷惑そうな目つきをしながらも、ボクを黒い目で見ていた。



























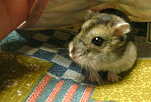
コメント 0